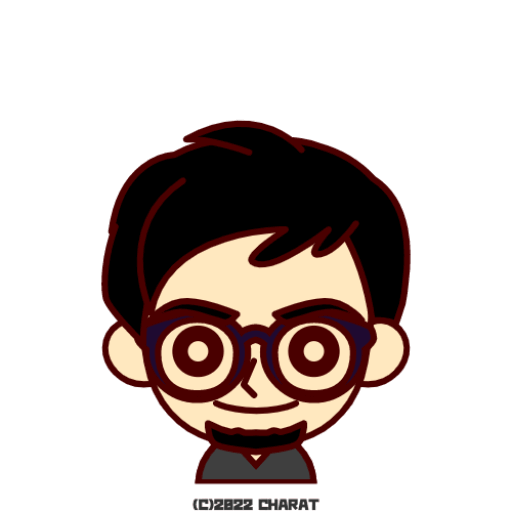「普段は車に乗っているけど、もっと気軽に使えるバイクがあったら便利だな…」
「125ccのバイクに乗りたいけど、普通免許だけじゃダメなんだっけ?」
「小型二輪の免許って、普通免許がありなら簡単に取れるのかな?」
そんな風に考えているあなたへ。普通自動車免許を持っていれば、小型限定普通二輪免許(以下、小型二輪免許)は驚くほどスムーズに、そしてお得に取得できます。
この記事を読めば、あなたの疑問はすべて解決します。
この記事でわかること
- 普通免許ありの場合の小型二輪免許取得のメリット
- 免許取得にかかる具体的な費用と期間
- 教習所での流れや注意点
- あなたにピッタリの125ccバイクの選び方
さあ、この記事を読んで、憧れのバイクライフへの第一歩を具体的にイメージしてみましょう!
普通自動車免許がある場合の小型限定普通二輪免許の取得メリット

原付二種のある暮らし・イメージ
普通自動車免許を持っている方が小型二輪免許を取得する最大のメリットは、なんといっても教習時間の大幅な短縮と費用の割引です。
通常、バイク免許を取得する際は多くの学科教習を受ける必要がありますが、普通免許があればそのほとんどが免除されます。
交通法規の知識がすでにあると見なされるため、技能教習に集中できるのです。
これにより、時間的にも金銭的にも大きなアドバンテージが生まれます。
忙しい社会人や学生の方でも、週末や空いた時間を利用して無理なく免許取得を目指せるでしょう。
また、125ccバイクは「原付二種」とも呼ばれ、50ccの原付バイクにはない多くのメリットがあります。
- 法定速度が車と同じ60km/h
- 二段階右折が不要
- 二人乗りが可能(免許取得後1年などの条件あり)
車の便利さと、バイクの手軽さの「いいとこ取り」ができるのが125ccバイクの魅力。
普通免許にプラスして小型二輪免許を取得することは、あなたの行動範囲をぐっと広げ、新しい世界を見せてくれる賢い選択なのです。
小型二輪免許で運転可能なバイクと原付二種スクーターの種類一覧
小型二輪免許で運転できるのは、総排気量が50ccを超え125cc以下のバイクです。
このクラスには、デザインも性能も多種多様なモデルが揃っており、選ぶ楽しさも魅力の一つです。
大きく分けると、クラッチ操作が不要で運転が簡単なAT(オートマチック)車と、自分でギアを変速する楽しさがあるMT(マニュアル)車があります。
【AT車の代表的なモデル】
| 車種 | 特徴 |
|---|---|
ホンダ「PCX」
 ホンダ・PCX公式 |
スタイリッシュなデザインと快適な乗り心地で大人気のスクーター |
ヤマハ「NMAX」
 ヤマハ・NMAX公式 |
スポーティーな走りと高い質感で所有満足度の高い一台 |
スズキ「アドレス125」
 スズキ・アドレス125公式 |
コンパクトで扱いやすく、通勤・通学の頼れる相棒 |
ホンダ「スーパーカブ C125」
 ホンダ・スーパーカブ C125公式 |
伝統的なスタイルと驚異的な燃費性能を誇る国民的バイク |
【MT車の代表的なモデル】
| 車種 | 特徴 |
|---|---|
ホンダ「モンキー125」
 ホンダ・モンキー125公式 |
小さくて愛らしい見た目ながら、所有する喜びと操る楽しさを満喫できる趣味性の高いバイク |
スズキ「GSX-S125」
 スズキ・GSX-S125公式 |
本格的なスポーツ走行が楽しめる、クラスを超えた性能を持つネイキッドバイク |
このように、スクーターから趣味性の高いバイクまで、あなたのライフスタイルに合った一台が必ず見つかるはずです。
125cc原付二種バイクの特徴と普通免許所有者が選ぶ理由
では、なぜ多くの普通免許所有者が、中型や大型ではなく125ccの小型二輪免許を選ぶのでしょうか。
その理由は、125ccバイクが持つ圧倒的なコストパフォーマンスと利便性にあります。
まず、維持費が非常に安い点が挙げられます。軽自動車税は年間2,400円と手頃で、任意保険も自動車保険に付帯できる「ファミリーバイク特約」を利用すれば、年間数千円から1万円程度で加入できる場合が多く、経済的負担を大きく軽減できます。
燃費性能も素晴らしく、モデルによってはリッター50km以上走るものも珍しくありません。毎日の通勤・通学で使えば、ガソリン代を大幅に節約できるでしょう。
さらに、車体がコンパクトで軽いため、取り回しが非常に楽です。狭い路地や混雑した市街地でもスイスイ走れ、駐車スペースにも困りません。
車ではためらってしまうような場所へも、バイクなら気軽に出かけられます。
「車を出すほどではないけれど、自転車や徒歩では少し遠い」そんな日常の「ちょっとした移動」を、楽しく快適な時間に変えてくれる。
それが、普通免許所有者が125ccバイクを選ぶ最大の理由なのです。
小型限定普通二輪免許の取得条件と年齢制限、視力検査などの基本情報

原付二種のある暮らし・イメージ
小型二輪免許を取得するためには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があります。
普通免許を持っている方も、改めて確認しておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 |
|
| 視力 |
|
| 色彩識別能力 |
|
| 運動能力 |
|
| 聴力 |
|
これらの条件は、教習所の入校時や免許センターでの手続きの際に適性検査で確認されます。
特に視力に不安がある方は、事前に眼科で検査を受けておくと安心です。
小型限定普通二輪免許の取得に必要な学科・技能教習時間のポイント
ここが、普通免許を持っている方が最もメリットを感じる部分です。
通常、免許を持っていない場合は26時限の学科教習と、段階に応じた技能教習が必要ですが、普通免許ありの場合はこれが大幅に短縮されます。
【普通免許ありの場合の最短教習時間】
| 免許の種類 | 学科教習 | 技能教習 |
| AT限定小型二輪 | 1時限 | 8時限 |
| MT小型二輪 | 1時限 | 10時限 |
ご覧の通り、学科教習はたったの1時限しかありません。
これは、交通法規を学ぶものではなく、二人乗りや危険予測など、バイク特有の内容を学ぶ時間です。そして、教習所卒業後に受ける学科試験も免除されます。
技能教習は、AT限定なら最短8時限、MTでも最短10時限で完了します。
これは、教習所のスケジュールにもよりますが、順調に進めば非常に短期間で卒業が可能であることを意味します。
この「時短」こそが、普通免許所持者にとって最大の魅力と言えるでしょう。
▼関連記事
指定自動車教習所の利用で小型限定普通二輪免許を取得する流れ

原付二種のある暮らし・イメージ
指定自動車教習所を利用して免許を取得するのが、最も一般的で安心な方法です。
試験場で直接技能試験を受ける「一発試験」という方法もありますが、合格率が非常に低いため、教習所に通うことを強くおすすめします。
教習所での流れは、おおむね以下のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 教習所選び・入校手続き |
|
| 適性検査 |
|
| 第1段階:基本操作の習得 |
|
| みきわめ |
|
| 第2段階:応用的走行 |
|
| 卒業検定 |
|
| 免許センターでの併記手続き |
|
▼関連記事
小型自動二輪車一発試験の流れと費用は?合格ポイントを徹底解説
教習所での技能教習や検定の内容と注意すべきポイント
バイクの運転は、車の運転とは全く感覚が異なります。普通免許を持っているからといって、油断は禁物です。
特に、技能教習や卒業検定では、いくつかの重要なポイントがあります。
【主な教習・検定課題】
- 引き起こし・取り回し
倒れたバイクを一人で起こし、エンジンをかけずに押して歩く練習。
車体の重さに慣れるための第一歩です。
- 一本橋
幅30cm、長さ15mの細い橋の上を、規定タイム以上かけてゆっくりと通過する課題。
バランス感覚が問われます。
- クランク・S字
狭い直角カーブやS字カーブを、パイロンに接触せず、足を着かずに通過する課題。
スムーズなハンドル操作と車体コントロールが必要です。
- 急制動
指定された速度から、短い距離で安定して停止する課題。正しいブレーキ操作が求められます。
【注意すべきポイント】
卒業検定は減点方式で行われます。一本橋からの脱輪、パイロンへの接触、エンスト(MT車)、転倒などは大きな減点、または一発で検定中止となる場合があります。
最も大切なのは「安全確認」です。乗車時、発進時、進路変更時、右左折時など、あらゆる場面でミラーと目視による確認が厳しくチェックされます。
普段、車を運転していると癖で怠りがちになることもあるかもしれませんが、「やりすぎかな?」と思うくらい大げさに首を振って確認する意識を持ちましょう。
最初は誰でもうまくいかないもの。焦らず、インストラクターのアドバイスを素直に聞いて、一つ一つの課題を着実にクリアしていくことが合格への近道です。
教習所コースとAT・MT選択の違い、最短取得期間を徹底解説
免許取得にあたり、多くの人が悩むのが「AT限定」と「MT」のどちらを選ぶかという点です。
それぞれの特徴を理解し、自分のバイクライフに合った方を選びましょう。
【AT(オートマチック)限定免許】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
【MT(マニュアル)免許】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
|
| デメリット |
|
【最短取得期間について】
教習所によっては「最短2日!」や「最短3日!」といった短期集中プランを設けている場合があります。
これは、1日に乗れる技能教習の上限時間(第1段階2時限、第2段階3時限)を毎日連続で予約し、スムーズに進んだ場合の理論上の最短日数です。
現実的には、仕事や学校の都合で毎日通うのは難しい方が多いでしょう。
週末だけを利用して通う場合、おおよそ1ヶ月程度を見ておくと無理のないスケジュールが組めます。
自分のライフスタイルに合わせて、通いやすいプランを選びましょう。
普通免許がある場合の小型限定普通二輪免許の取得費用と料金相場
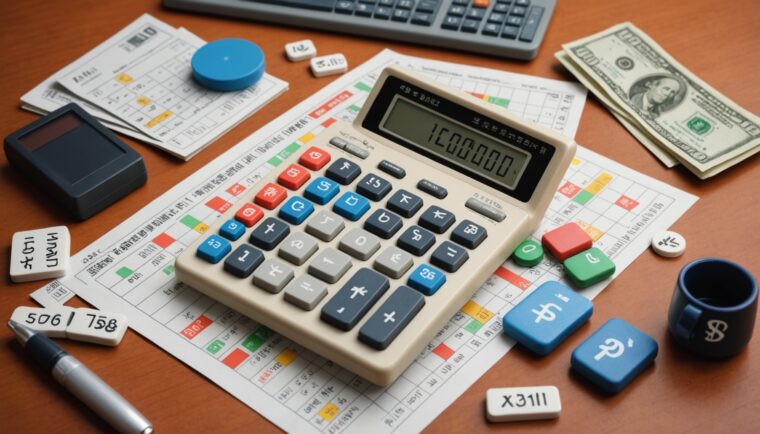
原付二種のある暮らし・イメージ
普通免許を持っている場合、小型二輪免許の取得費用はかなり抑えられます。
教習所や地域によって多少の差はありますが、おおよその相場は以下の通りです。
【普通免許ありの場合の料金相場】
- AT限定小型二輪免許: 8万円 〜 11万円 程度
- MT小型二輪免許: 10万円 〜 13万円 程度
この料金には、入校金、技能教習料、卒業検定料、教材費、適性検査料などが含まれているのが一般的です。
ただし、注意点もあります。この料金は、すべて最短時限で補習なく卒業した場合の金額です。
もし技能教習でつまずいてしまったり、卒業検定に不合格になったりした場合は、追加の補習料金や再検定料金が別途必要になります。
入校する際には、料金体系をしっかりと確認し、追加料金がどのくらいかかるのかも把握しておくと安心です。
キャンペーンなどで料金が割引になることもあるので、複数の教習所を比較検討してみるのも良いでしょう。
小型限定普通二輪免許の追加取得で免除される学科や手続き方法
前述の通り、普通免許を持っている方が小型二輪免許を追加で取得(併記)する場合、26時限の学科教習と、免許センターでの学科試験がまるごと免除されます。
これが最大のメリットです。
教習所を無事に卒業し、「卒業証明書」を受け取ったら、1年以内に住民票のある都道府県の運転免許センターで手続きを行います。
【免許センターでの併記手続きに必要なもの】
- 現在所持している運転免許証
- 指定自動車教習所の卒業証明書(有効期間1年)
- 申請書(免許センターにあります)
- 手数料(申請手数料と交付手数料で合計3,800円程度)
- 証明写真(申請書に貼付。免許センター内で撮影も可能)
手続きは非常に簡単です。窓口で書類を提出し、視力などの簡単な適性検査を受ければ、新しい免許証が即日交付されます。
試験がないため、緊張する必要もありません。平日に半日ほど時間を確保できれば、すべての手続きは完了します。
この手軽さも、追加取得ならではの魅力です。
道路交通法で定められた小型限定普通二輪免許での運転可能範囲

原付二種のある暮らし・イメージ
小型二輪免許で運転できる125ccバイクは、道路交通法上「普通自動二輪車」に分類されます。
そのため、50ccの原付バイクとは異なるルールが適用されます。
- 一般道路: 走行可能です。法定速度は自動車と同じ60km/hです。
- 高速道路・自動車専用道路: 走行することはできません。 標識に注意し、誤って進入しないようにしましょう。
- 二人乗り: 免許取得から1年が経過すれば、二人乗りが可能です(一部、二人乗りが禁止されている道路もあります)。
特に重要なのが「高速道路に乗れない」という点です。ツーリングなどで遠出を計画する際は、ルート設定に注意が必要です。
しかし、一般道での機動力は抜群で、街乗りから郊外へのショートツーリングまで、幅広いシーンで活躍してくれます。
小型限定普通二輪免許で乗れる車種と使用上の制限・注意事項
改めて、乗れる車種とルールについて整理しておきましょう。
- 排気量
50ccを超え、125cc以下のバイク。AT限定免許の場合は、その中でもAT車(スクーターなど)に限られます。
- ナンバープレート
51cc〜90ccは黄色、91cc〜125ccはピンク色のナンバープレートが交付されます。
- 保険
自動車の任意保険に「ファミリーバイク特約」を付帯できる場合があります。
これは、自分や家族が所有・使用する原付バイク(125cc以下)での事故を補償するもので、単独でバイク保険に加入するより保険料を大幅に節約できる可能性があります。
現在加入している自動車保険の契約内容を確認してみましょう。
ファミリーバイク特約は非常に便利な制度ですが、補償内容が対人・対物賠償に限られる場合や、搭乗者傷害保険が付帯しないケースもあります。
自分の身を守るためにも、補償内容はしっかりと確認し、必要であれば単独のバイク保険への加入も検討しましょう。
小型限定普通二輪免許取得後におすすめの125ccバイクと安全装備

原付二種のある暮らし・イメージ
念願の免許を取得したら、いよいよ愛車選びです。初心者の方でも安心して乗れる、おすすめのモデルをいくつかご紹介します。
【初心者におすすめの125ccバイク】
- ホンダ 「PCX」

ホンダ・PCX公式
「迷ったらコレ」と言われるほどの定番モデル。乗り心地が良く、燃費も抜群。スマートキーなどの先進装備も魅力で、通勤からツーリングまでオールマイティにこなします。
- ヤマハ 「NMAX」

ヤマハ・NMAX公式
スポーティーな走りを求めるならこちら。安定感のある足回りと力強いエンジンで、キビキビとした走りを楽しめます。
- ホンダ 「スーパーカブ C125」

ホンダ・スーパーカブ C125公式
クラッチ操作がない特殊なMT(自動遠心クラッチ)で、MT入門に最適。おしゃれなデザインと圧倒的な低燃費で、幅広い層から支持されています。
- スズキ「GSX-S125」

スズキ・GSX-S125公式
「本当に125cc?」と驚くほど本格的な作りのスポーツバイク。バイクを操る楽しさを存分に味わいたい方におすすめです。
【必須の安全装備】
バイクは車と違い、体が外部に露出しているため、安全装備は命を守るために不可欠です。
- ヘルメット
頭部を守る最も重要な装備。安全基準(PSC、SG、JISなど)を満たしたものを選びましょう。顔全体を覆うフルフェイスタイプが最も安全性が高いです。
- グローブ
転倒時の手の保護はもちろん、操作性の向上や疲労軽減にも繋がります。
- ジャケット・パンツ
肘、肩、背中、膝にプロテクターが入ったライディング専用のものがおすすめです。普段着とは比べ物にならないほど安全性が高まります。
- シューズ
くるぶしまで隠れる、バイク用のライディングシューズやブーツが理想です。
「ちょっとそこまで」の距離でも、必ずヘルメットとグローブは装着する習慣をつけましょう。
小型限定普通二輪免許とバイク保険の選び方・維持費のポイント
バイクライフを安心して楽しむためには、保険と維持費の知識も大切です。
【バイク保険の選び方】
自賠責保険(強制保険)だけでは、万が一の事故の際に相手への賠償が不十分になる可能性があります。
必ず任意保険にも加入しましょう。
- ファミリーバイク特約
自動車保険に付帯する形で加入。保険料が安いのが最大のメリット。
ただし、補償範囲やロードサービスなどの付帯サービスが限定的な場合も。
- 単独のバイク保険
バイク専用の保険として契約。保険料は高くなりますが、補償内容を自由に設計でき、ロードサービスなども充実しています。
自分の運転頻度や使い方、自動車保険の契約内容を考慮して、最適なプランを選びましょう。
【主な維持費】
- 軽自動車税: 年間2,400円
- 自賠責保険料: 年間数千円(契約年数による)
- 任意保険料: ファミリーバイク特約なら年間数千円〜、単独契約なら年間数万円〜
- ガソリン代
- メンテナンス費用: オイル交換、タイヤ交換など
車に比べると、維持費は格段に安く済みます。これも125ccバイクの大きな魅力です。
まとめ:小型限定普通二輪免許(125cc)についての総まとめ

原付二種のある暮らし・イメージ
今回は、普通自動車免許を持っている方が小型二輪免許を取得する際のポイントを、流れから費用、おすすめのバイクまで詳しく解説しました。
最後に、この記事の要点をまとめてみましょう。
【今回のまとめ】
- 普通免許がありなら、小型二輪免許は短期間・低コストで取得できる。
- 学科教習はたったの1時限で、学科試験は免除されるのが最大のメリット。
- 125ccバイクは法定速度60km/h、二段階右折不要で、街乗りの利便性が抜群。
- 維持費が安く、ファミリーバイク特約を使えば保険料も抑えられる。
- AT限定は手軽で安く、MTは操る楽しさと乗れる車種の多さが魅力。
125ccバイクが1台あるだけで、あなたの毎日はもっと自由で、もっとアクティブに変わるはずです。
通勤の満員電車から解放されたり、今まで知らなかった近所の素敵なお店を見つけたり、休日にふらっと隣町までツーリングに出かけたり…。
そんな新しい日常が、あなたを待っています。
この記事を読んで、「自分にもできそう!」と感じていただけたなら、ぜひお近くの教習所に資料請求や問い合わせをしてみてください。
その一歩が、新しい世界への扉を開く鍵になります。
▼関連記事
小型自動二輪車一発試験の流れと費用は?合格ポイントを徹底解説