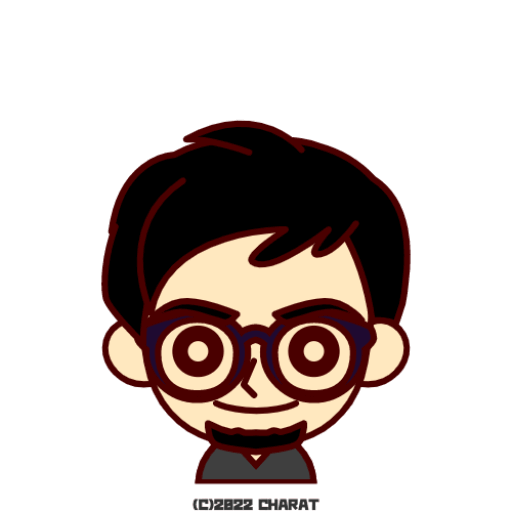「手軽にバイクに乗ってみたいけど、AT限定の小型二輪免許って、教習所ではどんなことをするんだろう?」
「普通免許は持っているけど、費用や期間はどれくらいかかるのかな?」
125cc以下のバイクを手軽に運転できる小型二輪AT限定免許。
通勤や通学、ちょっとしたツーリングに便利で、取得を検討している方も多いのではないでしょうか。
しかし、いざ教習所に通うとなると、具体的な教習内容や流れ、費用面で不安を感じてしまいますよね。
この記事を読めば、そんなあなたの悩みをスッキリ解決できます。
この記事でわかること
- 小型二輪AT限定免許の教習内容が具体的にわかる
- 免許取得までの流れや最短日数、費用がわかる
- AT限定で乗れるバイクや免許の選び方がわかる
- 卒業検定に合格するためのポイントがわかる
この記事を最後まで読めば、小型二輪AT限定免許取得に関するすべての疑問が解消され、安心して教習所に申し込む準備が整います。
小型二輪AT限定免許の特徴と取得のメリットを徹底解説

原付二種のある暮らし・イメージ
小型二輪AT限定免許は、正式には「普通自動二輪車免許(AT小型限定)」と言い、数あるバイク免許の中でも特に手軽に取得できる人気の免許です。
クラッチ操作が不要なAT(オートマチック)車に限定されているため、スクータータイプのバイクが主な運転対象となります。
自転車に乗れる感覚で気軽に運転できるのが最大の魅力で、車の普通免許を持っている方なら、最短2日〜3日で取得できる教習所も多く存在します。
この免許を取得することで、日々の移動が格段に便利になるだけでなく、行動範囲がぐっと広がり、新しい趣味や楽しみを見つけるきっかけにもなるでしょう。
維持費が安く燃費の良い125cc以下のバイクは、経済的なメリットも大きいと言えます。
小型二輪AT免許の取得条件と必要資格・年齢制限について
小型二輪AT限定免許を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、年齢は満16歳以上である必要があります。
視力に関しては、両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であることが求められます(メガネやコンタクトレンズの使用可)。片眼の視力が0.3に満たない場合や、一眼が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であることが条件となります。
また、信号機の色(赤・青・黄)を正確に識別できる色彩識別能力も必要です。
学力や運動能力については、教習所の入所時に簡単な適性検査がありますが、日常生活に支障がなければ特に問題になることはありません。
すでに普通自動車免許を持っている場合は、学科教習のほとんどが免제となり、技能教習に集中できるため、より短期間・低価格で免許を取得することが可能です。
小型二輪AT限定免許で運転できるバイクと車種一覧を紹介
小型二輪AT限定免許で運転できるのは、総排気量が125cc以下のAT(オートマチック・トランスミッション)バイクです。
クラッチ操作やギアチェンジが不要なスクータータイプが中心で、その手軽さから「原付二種」とも呼ばれ、非常に人気があります。
具体的な車種としては、以下のようなモデルが挙げられます。
| 車種 | 特徴 |
|---|---|
ホンダ「PCX」
 ホンダ・PCX公式 |
|
ヤマハ「NMAX」
 ヤマハ・NMAX公式 |
|
スズキ 「アドレス125」
 スズキ・アドレス125公式 |
|
ホンダ 「スーパーカブ C125」
 ホンダ・スーパーカブ C125公式 |
|
ホンダ 「CT125・ハンターカブ」
 ホンダ・CT125・ハンターカブ公式 |
|
これらのバイクは、車体がコンパクトで取り回しがしやすく、燃費が良いのが特徴です。二人乗りも可能で、法定速度も自動車と同じ60km/hまで出すことができます(一般道)。
通勤・通学から休日のツーリングまで、幅広いシーンで活躍してくれるでしょう。
普通・大型・小型二輪免許の違いとAT/MT限定別の選び方
バイクの免許は、排気量によって「小型限定」「普通」「大型」の3つに区分され、さらにそれぞれにAT限定とMT(マニュアル)の限定なしがあります。
| 免許の種類 | 総排気量 | 高速道路 | AT/MT | 特徴 | こんな人におすすめ |
| 小型限定 | 125cc以下 | 走行不可 | 両方あり |
|
|
| 普通二輪 | 400cc以下 | 走行可能 | 両方あり |
|
|
| 大型二輪 | 制限なし | 走行可能 | 両方あり |
|
|
AT限定かMT免許かで迷う方も多いでしょう。AT限定はクラッチ操作がないため、運転が非常に簡単で、エンスト(エンジンストール)の心配もありません。
一方、MT免許は自分でギアを操作する楽しさがあり、よりスポーティーな走りやバイクとの一体感を味わえます。
まずは手軽にバイクライフを始めたい、スクーターに乗りたいという方は小型二輪AT限定免許からスタートするのがおすすめです。
後からMTに乗りたくなった場合は、「限定解除審査」を受けることでMT免許にステップアップすることも可能です。
小型二輪AT免許取得後に広がる行動範囲と活用事例
小型二輪AT限定免許を取得すると、あなたの生活はよりアクティブで自由なものに変わります。
例えば、これまでバスや電車を乗り継いでいた通勤・通学路も、バイクならドア・ツー・ドアでスムーズに移動でき、満員電車のストレスから解放されます。
休日の過ごし方も大きく変わるでしょう。
ふらっと隣町のカフェまでランチに出かけたり、少し足を延ばして景色の良い場所までプチツーリングを楽しんだり。
車では入れないような細い道や、駐車場を探すのに苦労するような場所でも、小型バイクなら気軽に入っていけます。
また、燃費が良く維持費も安いため、ガソリン代や交通費の節約にも繋がります。
行動範囲が広がることで、新しいお店を発見したり、これまで知らなかった美しい風景に出会えたりと、日常の中に新しい発見と感動が生まれるはずです。
教習所での小型二輪AT教習内容と流れを詳しく解説

原付二種のある暮らし・イメージ
教習所での小型二輪AT教習は、バイクに全く乗ったことがない方でも安全に運転技術を習得できるよう、段階的かつ体系的なカリキュラムが組まれています。
教習は大きく分けて、実際にバイクを運転する「技能教習」と、交通ルールや安全知識を学ぶ「学科教習」の二つで構成されています。
普通自動車免許を持っている場合、学科教習はほとんど免除されるため、技能教習に集中することができます。
AT限定はクラッチ操作がない分、MT教習に比べて操作がシンプルなため、比較的スムーズに教習を進められる方が多いのが特徴です。
小型二輪AT限定免許の教習の段階・時限数・実施コースや練習方法
小型二輪AT限定免許の教習は、第1段階と第2段階に分かれています。
法律で定められた最短教習時限数は、所持している免許によって異なります。
| 所持免許 | 技能教習(最短) | 学科教習 |
| 普通免許あり | 8時限 | 1時限 |
| 免許なし・原付免許あり | 12時限 | 26時限 |
【技能教習】
技能教習は、教習所内のコースで指導員とマンツーマン(または少人数)で行われます。
目標は、バイクを安全に操作し、交通法規に従った運転ができるようになることです。
| 段階 | 時限数 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1段階(基本操作の習得) |
|
|
| 第2段階(応用走行と交通法規の実践) |
|
|
技能教習の内容をまとめました。
| 段階 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1段階(基本操作の習得) | 車両の取り回し・引き起こし | エンジンをかけずに押し歩きや引き起こしを行い、バイクの重さに慣れる |
| 第1段階(基本操作の習得) | 基本姿勢と発進・停止 | 正しい乗車姿勢、スムーズな発進と安定した停止を練習する |
| 第1段階(基本操作の習得) | 直線でのバランス | 一本橋など低速での直線走行でバランス感覚を養う |
| 第1段階(基本操作の習得) | カーブ走行 | S字カーブやクランクを安定して走行する練習 |
| 第2段階(応用走行と交通法規の実践) | 坂道発進 | 坂道で停止後、後退せずにスムーズに発進する練習 |
| 第2段階(応用走行と交通法規の実践) | 急制動 | 指定速度から短い距離で安全に停止する練習 |
| 第2段階(応用走行と交通法規の実践) | 見通しの悪い交差点 | 安全確認の手順を学び、実践する |
| 第2段階(応用走行と交通法規の実践) | シミュレーター教習 | 危険予測や交通状況を想定したシミュレーションを行う |
【学科教習】
学科教習は、座学形式で行われます。
- 普通免許なしの場合(26時限)
交通法規、標識、安全運転の知識、応急救護など、運転に必要な知識全般を学びます。
- 普通免許ありの場合(1時限)
主に二輪車の特性や安全運転に関する内容を学びます。
練習は、指導員が丁寧に教えてくれるので、焦らず一つ一つの課題をクリアしていくことが大切です。
不安な点があれば、遠慮なく質問しましょう。
教習所で実施される適性検査と視力検査のポイント
教習所に入所すると、まず最初に行われるのが適性検査です。
これは運転免許を取得するための最低限の身体的な基準を満たしているかを確認するためのもので、難しい試験ではありません。
| 検査項目 | 基準・内容 |
|---|---|
| 視力検査 |
|
| 色彩識別能力検査 |
|
| 聴力検査 |
|
| 運動能力検査 |
|
これらの検査は、安全に運転できるかどうかを判断するためのものです。
リラックスして臨めば、ほとんどの方が問題なくクリアできます。
教習所選びのコツと利用時の料金・費用相場や最短日数

原付二種のある暮らし・イメージ
教習所選びは、免許取得を成功させるための重要なステップです。
料金だけでなく、通いやすさや教習の予約の取りやすさも考慮しましょう。
自宅や職場、学校から通いやすい場所にあるか、送迎バスのルートはどうかなどを確認します。
【料金・費用相場】
小型二輪AT限定免許の教習料金は、所持免許や教習所によって異なりますが、おおよその相場は以下の通りです。
- 普通免許あり: 8万円~12万円程度
- 免許なし・原付免許あり: 15万円~20万円程度
この料金には、入学金、教習料金、検定料金、教材費などが含まれているのが一般的です。
ただし、補習や再検定が必要になった場合は、別途追加料金がかかることが多いので、総額でいくらかかるのかを入所前にしっかり確認しておきましょう。
【最短日数】
法律で定められた最短時限数をストレートでクリアした場合の最短日数です。
- 普通免許あり: 2日~3日(合宿免許や短期集中プランの場合)
- 通学の場合: 予約の状況にもよりますが、1週間~1ヶ月程度が目安です。
技能検定・卒業検定・試験の流れと合格のための注意事項

原付二種のある暮らし・イメージ
教習の最終関門が卒業検定です。これは、教習所で学んだ運転技術と知識が身についているかを判断するための技能試験で、これに合格すれば教習所を卒業できます。
検定は、教習所内の定められたコースを一人で走行し、指導員(検定員)が採点します。
【検定の流れ】
- 検定の説明: 試験官からコースや採点基準、注意事項についての説明があります。
- 走行準備: ヘルメットやプロテクターを装着し、バイクの点検を行います。
- コース走行: 指示されたコースを走行します。一本橋、S字、クランク、坂道発進、急制動など、教習で練習した課題が含まれます。
- 合格発表: 走行終了後、合格かどうかが発表されます。
【合格のための注意事項】
卒業検定は100点からの減点方式で、持ち点が70点以上で合格となります。
以下の点に注意して、落ち着いて臨みましょう。
- 安全確認を怠らない
乗車前、発進時、進路変更時、右左折時など、全ての場面でミラーと目視による安全確認を徹底しましょう。
確認不足は大きな減点対象です。
- 法規走行を守る
一時停止や速度超過など、交通ルールをしっかり守りましょう。
- 課題は慎重に
一本橋からの脱輪やパイロンへの接触は即検定中止となる場合があります。
焦らず、練習通りに慎重にクリアしましょう。
- 完走を目指す
多少のミスは気にせず、まずは最後まで走りきることが大切です。
最も重要なのは、リラックスすることです。緊張しすぎると普段できることもできなくなってしまいます。
「練習の成果を見せる場」と考え、平常心で挑みましょう。
小型二輪AT限定解除やMT教習へのステップアップ方法を解説
小型二輪AT限定免許を取得した後、「やっぱりマニュアル車にも乗りたい」「もっと大きなバイクに挑戦したい」と思うこともあるかもしれません。
その場合、限定解除やステップアップという形で、より上位の免許を取得することが可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| AT限定解除 |
|
| 普通二輪免許へのステップアップ |
|
このように、まずは手軽な小型二輪AT限定からバイクライフを始め、後から自分の興味やライフスタイルの変化に合わせてステップアップできるのも、この免許の魅力の一つです。
▼関連記事
小型二輪ATから普通二輪MTへ!限定解除に必要な費用と流れを徹底解説
よくある質問と回答集:入所手続き・予約・キャンセル・変更
ここでは、小型二輪AT限定免許の教習を検討している方によく見られる質問とその回答をまとめました。
Q1. 入所手続きには何が必要ですか?
A1. 一般的に、以下のものが必要になります。
- 住民票の写し(本籍地記載のもの): 発行から3ヶ月または6ヶ月以内のもの。
- 本人確認書類: 健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど。
- 運転免許証(お持ちの方): 普通免許など、他の免許証をお持ちの場合は必ず持参してください。
- 印鑑(認印)
- 教習料金
- メガネ・コンタクト(必要な方) 教習所によって異なる場合があるため、事前に必ず確認しましょう。
Q2. 教習の予約はどうやって取るのですか?
A2. 多くの教習所では、受付窓口での直接予約、電話予約、インターネットの予約システムを利用した予約が可能です。
特に技能教習は、希望の時間帯が埋まりやすいこともあるため、早めに予約することをおすすめします。
Q3. 急な用事で教習をキャンセルしたい場合はどうなりますか?
A3. キャンセルポリシーは教習所によって異なりますが、多くの場合、予約日の前日や当日のキャンセルにはキャンセル料が発生します。
キャンセルや変更をしたい場合は、できるだけ早く教習所に連絡しましょう。
まとめ:小型二輪AT限定教習で押さえておきたい総まとめと安全運転のポイント

原付二種のある暮らし・イメージ
今回は、小型二輪AT限定免許の教習内容から取得までの流れ、費用や乗れるバイクについて詳しく解説しました。
AT限定の小型二輪免許は、バイクライフを始める第一歩として最適な選択肢の一つです。
【今回のまとめ】
- 小型二輪AT限定免許は、125cc以下のスクータータイプが運転でき、最短2日で取得可能。
- 教習内容は、バイクの基本操作から始まり、段階的に応用走行まで学べるので初心者でも安心。
- 費用は普通免許ありで8万円~12万円が相場。キャンペーンを活用すれば更にお得に。
- 卒業検定は、安全確認を徹底し、落ち着いて臨むことが合格の鍵。
- 取得後も限定解除や普通二輪へのステップアップが可能。
免許取得はゴールではなく、安全で楽しいバイクライフのスタートです。
教習所で学んだ知識と技術を忘れず、常に「かもしれない運転」を心がけ、周囲への思いやりを持った運転をしてください。
ヘルメットやプロテクターを正しく着用し、定期的なバイクのメンテナンスも欠かさず行いましょう。
この記事が、あなたのバイクライフへの挑戦を後押しできれば幸いです。
▼関連記事
小型二輪ATから普通二輪MTへ!限定解除に必要な費用と流れを徹底解説